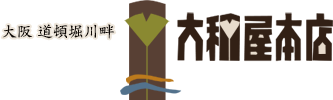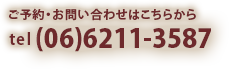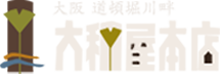「大阪」の記事一覧
『くいだおれ』の本来の意味は・・・。

今日の『道頓堀川』は年に一度の
『船乗り込み』!
毎年、
『大阪松竹座』で七月から始まる
『七月大歌舞伎』を宣伝する恒例行事で、
『道頓堀川』の初夏の風物詩です。
これを見るととうとう『夏』本番!ですね。
今日は一つまじめな話を。
大阪の食べ物といえば、
『たこ焼き』『お好み焼き』
『焼そば』『串カツ』『うどん』などなど・・・。
そして、
これら”安くておいしい”ものが多いことから
大阪は『くいだおれの町』
といわれていますが、
実は、
これは『ダジャレ』で
本来の意味とは全く違うんですね。
本当はもっともっと
『大阪人』の切なる思いが込められた言葉なんです。
このブログでもよく書きますが、
9世紀ごろまで大阪の中心には物を運んだりするため
“堀”がたくさんあり、また”川”がたくさんありました。
“川”がたくさんあれば、
『橋』もその数だけありました。
そのため、
大阪には今も多くの『○○橋』という地名が今も多く残っています。
その『橋』ですが昔は、
“橋”を架けることができたのは幕府と
莫大な財産を持っている個人だけが架けることが出来ました。
(例えば、『淀屋橋』など。)
また、
町内の人たちが少しずつお金を集めて架けられた『橋』もありました。
そんな”橋”は、昔も今も
架けるには莫大な費用がかかりました。
もちろん、架けてからの補修などの費用もたいへんかかり、
『杭ひとつ取り替えるだけでも町内は倒れる』
とまでいわれたそうです。
そのことから、
『杭倒れ』⇒『くいだおれ』から
大阪は『くいだおれの町』と呼ばれるようになるのです。
それだけに『大阪人』は『橋』を大切にしてきたのです。
今の私たちが忘れかけている
本当の『大阪人』の心かもしれませんね。
空堀だけど心は・・・。

今日は一日サッカーでしたね!
ワールドカップが
これだけ盛り上がるとは
誰が思ったでしょう。。
決勝リーグから
ほんとにすごいゲームになりそうです。
今日は谷町線にある
大阪で有名な商店街、
『空堀商店街』の由来をご紹介。
『空堀』という名前ですが、
その前に。
大阪には”○○堀”なんて名前多いですよね。
例えば、大阪の中心を東西に走る『土佐堀』や、
西区にある『江戸堀』に心斎橋の『長堀』など。
これらの”○○堀”というのは昔、その名の通り”堀”だったそうで、
その名前もそれぞれゆかりがあるそうです。
(今回は省きますが・・・。)
それで、話しはもどって”空堀”です。
この『空堀』もちゃんと由来があり
大阪城を築城したときに掘られた堀なんですが 、
その名の通り”堀”が、”空”(カラ)だったから
『空堀』と呼ばれるようになったそうです。
なんとまあわかりやすい。
そんな『空堀』も、
今では大阪らしさを残す『空堀商店街』となり、
我々のカラカラに乾いた心を”人情”という水で満たしてくれます。
また、
夏のはも料理も心を満たしてくれますよ!
http://www2.489ban.net/v4/client/plan/detail/customer/yamatoyahonten/plan/20664
大阪の道路の真ん中にある謎の木・・・。

6月も下旬に入り
梅雨にも入り
激しい雨が降ったり止んだり。
少しずつ夏に向けて
季節が変わり始めようとしています。
さて。
“谷町筋”より西側の『瓦町』を
真っ直ぐ北へ向かっていくと、
東西に伸びる長い道があります。
(写真では遠くからで見にくいですが・・・。)
『谷町』でいうと”7丁目”のところ。
道路の真ん中においおいと繁っている謎の木が!?
この木はその名も『楠木大明神』
(くすのきだいみょうじん)と呼ばれる楠。
地元ではよく知られているなんとも堂々とした楠なのです。
その昔、
この地には『本照寺』というお寺があったのですが、
昭和12年、道路拡張工事のためお寺は移転させられました。
しかし、この”楠”は
繁栄をもたらすといわれる蛇(巳)がすんでいると信じられ、
移動させたり、ましてや切ったりすると”タタリ”!が起こると信じられ、
今もここにあるのです。
残念ながら、
“楠”は数十年前に枯れてしまっているのですが、今でも大事にされています。
いつになったら終わることやら・・・。

今日は雨も降らず
蒸し暑い一日。。
こんな日はクーラーのきいた部屋で
ゆっくり読書というのもよいかも。
ちなみに私事で恐縮ですが、
最近はまった本は
『宮本 輝』さんの
長編小説で自伝的傑作。
『流転の海』シリーズ。
タイトルの『流転の海』が出版されたのが
1984年でかれこれ26年!!
(私が四歳の時ですか・・・。)
今年に入って出版された
第五部の『花の回廊』で終わるといわれていたのですが
結局、
まだまだ続くそうで
第六部、もしかしたら第七部までになるんだそう。
当時から
読んでいるファンからは
『いつになったら終わるんだ!』という怒りの声や
『私が死ぬまでになんとか終わって』という願いであったり
はたまた、
『ここまできたら終わらないで欲しい』など、意見は様々。
なんだかんだいっても
読者は『のぶちゃん』の成長を楽しみにしているだけなんですけど。。
四半世紀にわたり読まれ続けてきた
『流転の海』シリーズ。
いつになったら終わることやら・・・。
次は『のぶちゃん』、中学生くらいかな。。
古都、大阪の港は・・・。

昨日のサッカーは負けたけど、
なかなかいい試合でしたね。
ここ最近の
日本の試合の中でも見ごたえのあり、
最後までハラハラドキドキでした。。
今日は
大和屋本店からも歩いていける
『高津宮』をご紹介。
その昔、
『高津宮』の東側にまだ海が広がっていた頃。
その東側のあたりにあったといわれる”難波津”は瀬戸内海との
水路の拠点として各地からさまざまな物が行き来していました。
そんな”難波津”の高台に位置する『高津宮』は
“難波津”より”高いところ”にあるということから
『高津宮』と名づけられたといわれています。
また、
『高津宮』は由緒正しい神社で、
小学校の歴史にも出てきた『仁徳天皇』ゆかりの神社。
『難波に都をつくる。是を高津宮と謂う』といわれた、
ところでもあるんですね。
今でこそ
“奈良”や”京都”などといわれてますが、
大阪にもこういった”都”が置かれたところが結構あるんですよ!